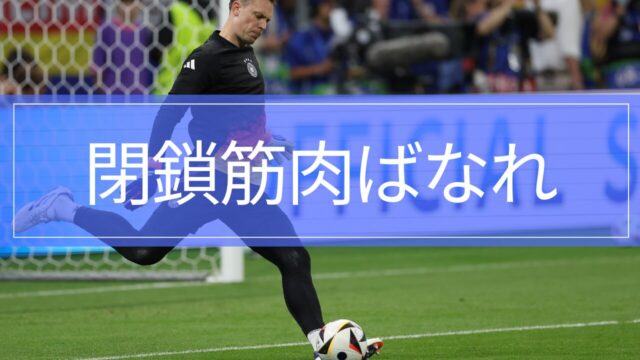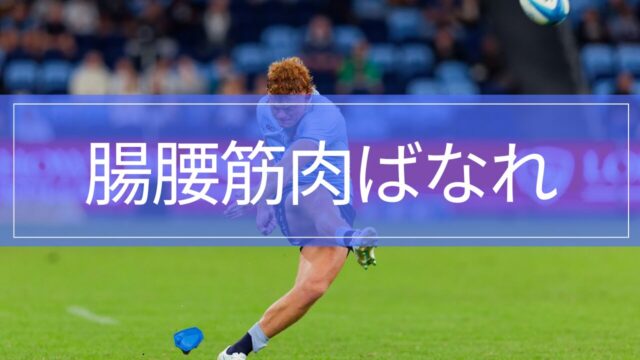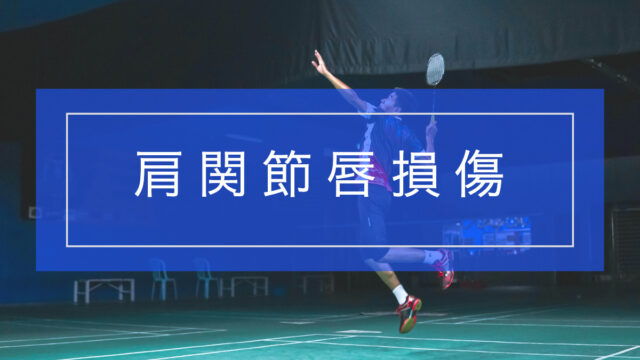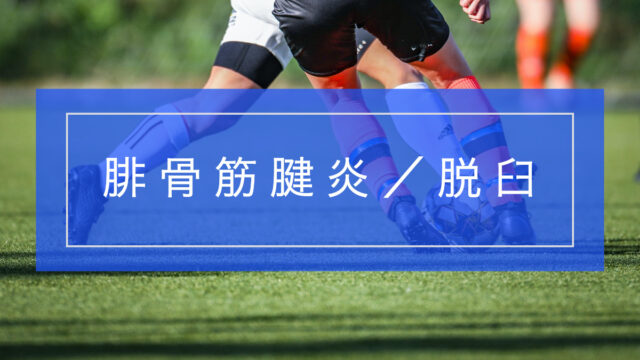今回はリトルリーガーズショルダー(上腕骨近位骨端線離開)になってしまったときの対処法について書いていきます。
少年野球選手は肘のケガが多いですが、肩にも成長期特有のケガが存在します。
今回はそんなにリトルリーガーズショルダーついて解説していきたいと思います!
目次
リトルリーガーズショルダーとは?
リトルリーガーズショルダー(Little Leaguer's shoulder:LLS)はその名の通り、リトルリーグ所属の学童期の野球選手に起こる肩の骨端線損傷の一つです(図1)。
正式には、上腕骨近位骨端線離開と呼ばれており、重症度はⅠ〜Ⅲ度と分類されています。
(Ⅰ型:骨端線外側の部分的な拡大を認める。Ⅱ型:骨端線全体の拡大を認める。Ⅲ型:骨頭の滑りを認める)
骨端線は成長軟骨とも呼ばれ、骨の成長に貢献しています。
成長期には脆弱な組織のため、繰り返しのストレスが加わると離開して痛みが生じてしまいます。

図1:リトルリーガーズショルダーのレントゲン画像。
患側の骨端線(白矢印)が健側に比べて開いていることが分かります。
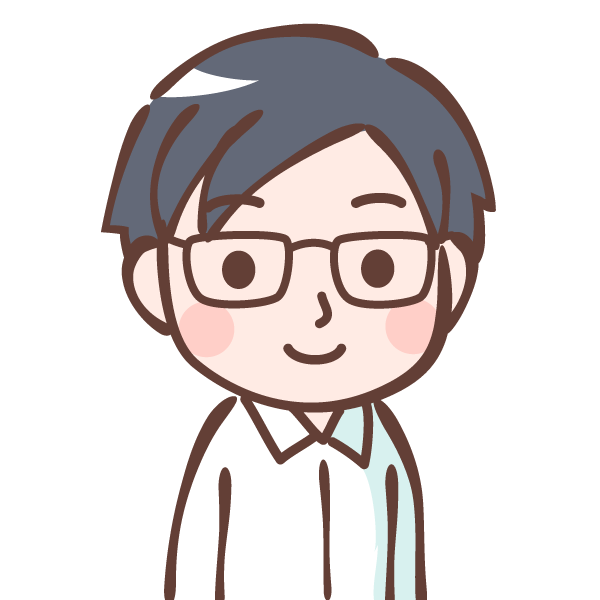
リトルリーガーズショルダーが起こりやすいシーン
リトルリーガーズショルダーは、学童期の野球選手が肩を捻る動作を繰り返すことで起こりやすいと言われています。
そのため、野球の投球動作で肩を大きく開くときに痛みが誘発されやすいとされています。

リトルリーガーズショルダーのよくある症状
投球動作時に、肩の痛みを訴えます。
また、肩を開く方向に力を加えると痛みが誘発される場合も多いです。

病院で行う検査
レントゲン検査を行い、肩の骨端線離開の有無を検査します。
また、エコーでも一部の骨端線離開をチェックすることも可能です。
症状が強い場合は、MRI検査で炎症の程度を確認をすることもあります。
画像検査の他には、問診(痛みが出た状況の確認など)、触診(痛みのある場所のチェック)、スペシャルテスト(HERT、外旋抵抗時痛)などを行います。

リトルリーガーズショルダーと診断されたら
基本的には保存療法でリハビリを行ないます。
Ⅰ型、Ⅱ型は痛み基準で少しずつリハビリを進めていきます。
一方で、Ⅲ型は滑りが大きくならないかレントゲンでチェックを行いながら復帰を目指します。
リトルリーガーズショルダーのリハビリテーション
基本的にはこの保存療法でリハビリを行い、症状の改善を目指します!
期間は目安ですので、自分に合った進め方をしましょう!
✅ 患部の炎症を抑える
★リハビリ後期
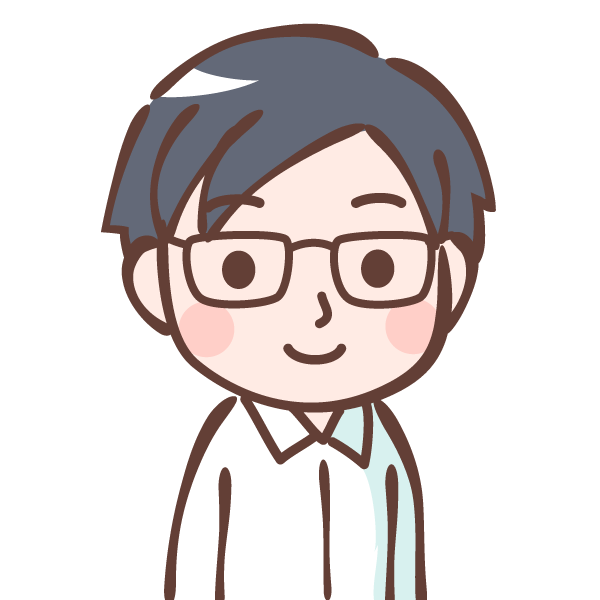
1〜3週間目安で力を入れても痛くなくなるので、そうなったら次のステップに進みましょう!
・肩の腱板筋の筋トレ!(←チューブなどで筋肉を鍛える)
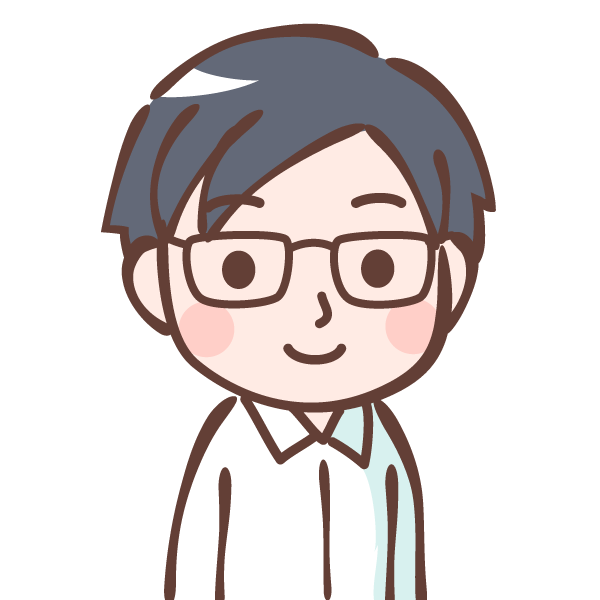
トレーニング後に痛みが悪化していないかチェックをしましょう!
・スポーツ活動を徐々に再開!(←フォームに注意)
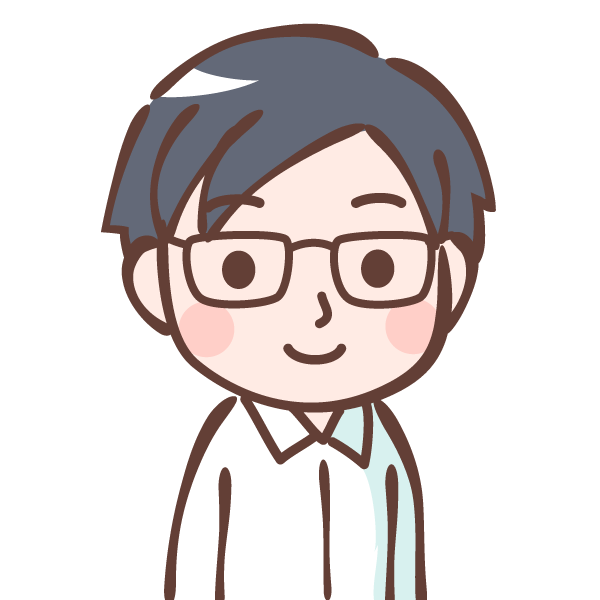
まとめ
ここまで、リトルリーガーズショルダーの方針やリハビリテーションについて書いてきました。
リトルリーガーズショルダーはしっかりリハビリをしないと長引きやすいケガですので、基本をしっかりおさえながらリハビリをしていきましょう!

「もっとこれが知りたい!」「こんな記事を書いて欲しい!」「ケガのことを相談したい!」
などご要望をお受けしています!
〈お問い合わせ〉からお気軽にご連絡ください!